将来のお金の不安って、どうしてもゼロにはなりません。
「増やしたいけれど、何から始めればいい?」
「保険で本当に資産運用なんてできるの?」
そんな声をよくいただきます。
でも実は、保険は“守るだけの道具”ではありません。
正しく設計すれば、家族の安心と資産形成の両方を同時に叶える、とても強力なツールになります。
今回は、僕が普段セミナーでも“ここまではなかなか話さない”という、リアルな設計やシミュレーション、出口戦略までを丁寧にまとめました。
「保険での資産運用ってどういうもの?」という方でもスッと読めるように噛み砕いて解説しますね。
保険運用は商品選びより“設計”が9割
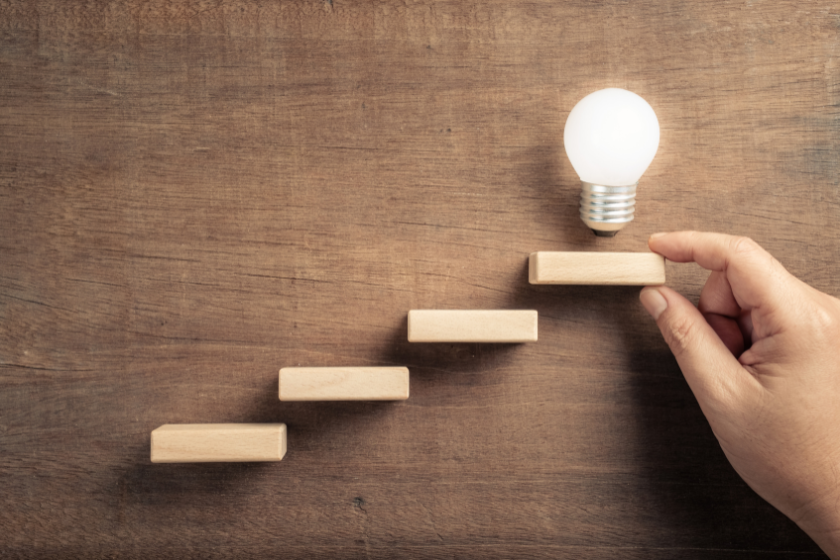
まずは「3つのタンク」で家計を分けることから
いきなり積み立て額や商品を考える人が多いのですが、実はその前にやるべきことがあります。
それが 家計の“3層タンク”をつくること。ここができていないと、どんな商品を選んでもブレやすくなってしまうんですね。
●タンク①:生活防衛資金(現金)
突発的な支出でも冷静でいられる“命綱”。
3〜12ヶ月分の生活費はここに置いておき、絶対に投資しないお金です。
●タンク②:起動資金(短期〜中期で使うお金)
教育費・旅行・引っ越し・事業資金など、数年以内に使う予定があるお金。
いつでも引き出せるNISAなどがこのタンクの担当。
●タンク③:長期資産(5〜10年以上使わないお金)
10年以上動かさない“未来のための資産”。
ここにこそ、保険を活用する意味があります。
生命保険の機能を持ちながら、長期での運用を掛け合わせられるからです。
この「タンク分け」ができるだけで、途中でブレて解約してしまう失敗をほぼ防げます。
では、この土台の上にどんな設計が成り立つのか、ここから具体的に見ていきましょう。
保険運用はこの3パターンが“鉄板”設計

普段の相談でもほぼ必ず登場するリアル設計
ここでは、実際に行っている3つの代表的な設計を紹介します。
① 教育資金 × 二段構えの設計
お子さんが3歳で、大学まであと15年あるとします。
この期間を利用して毎月2〜3万円を保険で長期積み立て。
ここは “育てるタンク(長期)” です。
そして、高校・大学入学など 数年以内に使う部分はNISAで別口に確保。
- 短期 → NISA
- 長期 → 保険(運用+生命保険付き)
この 二段構え が最強なんですね。
さらに重要なのが、満期設定を短くしないこと。
60歳満了などにしてしまうと、そこで「複利」が止まります。
雪だるまが大きくなる途中で転がすのをやめてしまうようなもの。
僕は 80歳満了 をおすすめしています。
② 老後資金 × 年金化の設計
「NISAもiDeCoもやってるけど、正直足りる気がしない…」
そう感じている方、とても多いです。
例えば月5万円を20年積み立てると元本は1200万円。
これを 3.5〜5%で運用 できる設計に入れると、
- 3.5%運用 → 約1690万円
- 5%運用 → 約2030万円
銀行より明らかに効率がいいんですね。
そして60〜80歳のタイミングで
毎年100万円ずつ「減額・部分解約」をしながら切り崩す。
いわば “自分で作る年金” です。
しかも死亡保障もセット。
生きてても使える、亡くなれば残せる──まさに 二刀流(大谷選手) です。
③ 相続対策 × 色分け設計
実はお金の相談で一番多いのが 相続の揉めごと。
現金ならまだしも、不動産が絡むとややこしい。
でも保険なら、受取額を指定して 色分け できます。
- 前妻の子 → 1000万円
- 妻 → 2000万円
- 次男 → 教育費として500万円
さらに死亡保険金には 非課税枠 もあるので、相続税対策としても有効。
では、こうした設計が実際にどのように増えていくのか。
ここからは“数字の世界”でイメージをつかみましょう。
出口戦略が「運用の9割」を決める
20年後に2030万円。ではどう受け取る?
月5万円 × 20年 = 元本1200万円。
これを5%で運用すると 約2030万円 に育ちます。
保険で運用する魅力はここから。
僕が死んだ場合、死亡保障2800万円 が家族に届く設計です。
つまり、
- 生きている間 → 残高が増える
- もしもの時 → 大きな保障が出る
この「育てながら守る」が、投資信託やNISAとの決定的な違い。
出口は3つだけ覚えればOK

① 減額・部分解約(年金化)
生活費・教育費に合わせて毎年100万円ずつ切り崩すなど。
② 契約者貸し付け
崩さずに一時的に借りられる機能。
返す前提ならかなり便利。
③ 受取人の設計(相続の色分け)
揉めごとを避け、家族の安心に直結。
とはいえ、保険運用には誤解されがちな点もあります。
ここもしっかり押さえておきましょう。
誤解されやすいポイントと、見直しのタイミング
① 手数料が高い?
手数料というより“運用+保証の代行料”。
自分で投信と保険を組み合わせるより合理的なケースが多い。
② 元本割れが怖い?
短期のお金を入れなければほぼ問題なし。
10年以内に解約すると減りやすい → だからタンク分けが大切。
③ 外貨建ては危険?
為替リスクはメリットにもデメリットにもなる。
僕はドル建て保険のような「外貨換算の積立」は設計しません。
理由は
- 為替リスク
- 為替の往復手数料
- 解約時も手数料
など。
見直しは“人生のイベント”ごとに
保険は入って終わりではありません。
家族構成が変われば、必要な保障も出口戦略も変わります。
- 子どもが生まれた
- 進学
- 自宅購入
- 手が離れるタイミング
- 55歳・60歳・65歳など節目
最低でも 2〜3年に1度は点検 を。
そして最後に、今日の内容をさらに深く学べる機会を用意しています。
もっと学びたい方へ──“お金の増やし方勉強会”を作りました

保険は守りの道具でありながら、設計次第で“増やす”こともできるとても強力な手段です。
僕自身、株・FX・不動産、いろいろ経験してきました。
その結果たどり着いたのが、
「守りながら増やす」という考え方。
それを体系的にまとめたのが、
初心者でも安心して参加できる お金の増やし方勉強会 です。
中学生の次男にもわかるように、かみ砕いて丁寧に話しています。
今日の話を読んで「もっと知りたい」「自分ごとにしたい」そう感じた方は、気軽に覗いてみてくださいね。
お金の増やし方をわかりやすく解説