「投資って、なんだか怖い…」
そう感じたことはありませんか?
ニュースやネットで「投資のリスク」という言葉を目にすると、
「大きく損すること」や「お金がなくなること」を想像して不安になる方も多いでしょう。
でも実は、投資におけるリスクとは「怖いこと」ではなく、“結果のブレ(不確実性)” のこと。
仕組みを理解し、コントロールできるように整えることで、リスクはむしろ“味方”になります。
この記事では、初心者がまず知っておきたいリスクの本質と、向き合い方をわかりやすく解説します。
読み終える頃には、「リスク=不安」から「リスク=管理できるもの」に変わるはずです。
リスク=不確実性(ブレ幅)である

投資で言うリスクとは、結果がどれだけ読めないか=**“ブレ幅”**のことです。
- 例)定期預金:年0.○%などでブレが小さい → リスク小
- 例)株式・投資信託:+10%〜-10%と値動きがある → リスク大
ここで大切なのは、「どちらが正しいか」ではなく、自分が許容できるブレ幅かどうか。
リスクは避けるものではなく、理解して備えるものなのです。
👉 次に、リスクの中でも「良いリスク」と「悪いリスク」があることを整理しましょう。
良いリスクと悪いリスクの違い
投資には「取るべきリスク」と「避けたいリスク」があります。
悪いリスク(避けたいもの)
- 仕組みを理解せずになんとなく買う
- 生活費まで投資に回し、資金繰りを圧迫
- 出口(売却基準・期間)を決めずに場当たりで判断
悪いリスクとは、投資の仕組みを理解せずに行動した結果、自分の生活や資産を不必要に危険にさらしてしまうものです。
たとえば、よく分からない商品を「なんとなく良さそうだから」と買ってしまうことや、生活費まで投資に回してしまい日々の資金繰りが苦しくなるケースが当てはまります。
また、出口戦略を考えずに場当たり的に売買を繰り返すと、結果的に大きな損失を抱えるリスクにもつながります。
こうしたリスクは、知識不足や計画性の欠如から生まれるものであり、できる限り避けるべきです。
良いリスク(取りに行く価値あり)
- 仕組みと特性を理解して自分で選んだ商品
- 分散・積立・長期でブレを均す設計
- 目標・期間・出口を決めた計画的な運用
一方で良いリスクとは、投資の仕組みを理解し、自分の目的や許容度を踏まえたうえで取るリスクのことです。
たとえば、株式や投資信託のように値動きの幅はあるものの、長期的に見れば資産を成長させる可能性が高い商品を選ぶことは「良いリスク」といえます。
また、分散投資や積立投資を組み合わせることで短期的なブレを抑え、計画的に成果を得ることも含まれます。
目標額や投資期間、出口戦略をあらかじめ設定しておけば、不確実性を「管理できるリスク」に変えることが可能になります。
こうしたリスクは、将来の資産形成にとって積極的に取りに行く価値があるのです。
Point:リスクはゼロにできません。
だからこそ「見える化 → 分散 → 時間分散」で“管理可能なリスク”に変えることが王道です。
👉 では、初心者がつまずきやすい「落とし穴」も押さえておきましょう。
よくある落とし穴:「減らない=増えないリスク」

「元本保証で安心」「ほとんど減らない」が魅力の商品は、
実は 将来に必要な額まで“育たない” という別のリスクを抱えがちです。
- 例)定期預金・低利回り商品・毎月分配型投信 など
安心感はありますが、インフレや長寿化時代では資産が実質目減りする可能性もあります。
つまり、安全=正解ではないのです。
目的(教育費・老後資金 等)と到達可能性で判断する必要があります。
👉 では、どうすれば「自分に合ったリスクのとり方」ができるのでしょうか?
自分はどんなリスクなら受け入れられる?
怖さの正体は「知らないこと」であるケースがほとんどです。
小さく理解 → 小さく実践 → 振り返り を繰り返すことで、不安は“管理”に変わります。
まず考えるべき2つの質問はシンプルです。
- 目的と期限は?(いつ・いくら必要?)
- 許容できるブレ幅は?(年単位で何%なら心穏やかでいられる?)
👉 これを踏まえて、初心者が実際に動くためのステップを紹介します。
初心者が最初にやるべき4ステップ
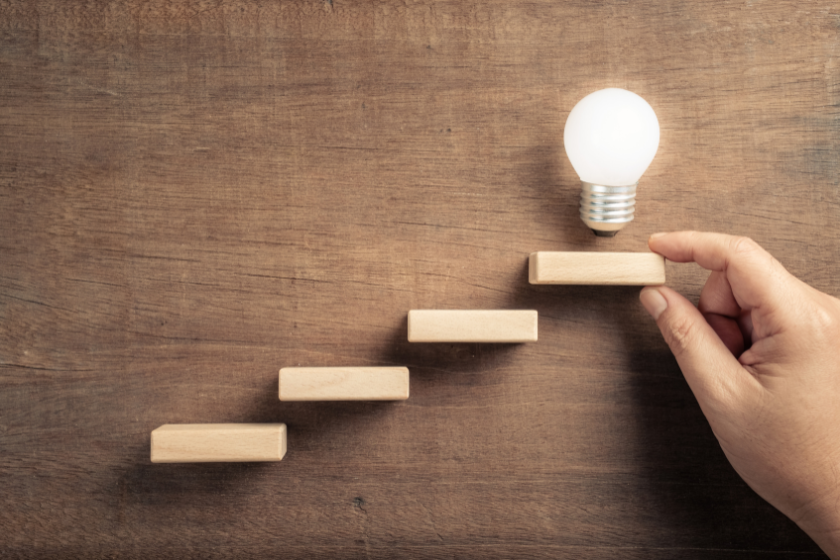
① 小さく分けて始める
いきなり100万円ではなく、月1〜2万円などから。
余裕資金に応じて“あなたにとっての小ささ”を基準にすることが大切です。
② 時間を武器にする(積立×長期)
ドルコスト平均法的な時間分散でブレを均し、5〜10年の視点で果実を収穫。
③ 情報の“質”を上げる
SNSや動画の噂だけで決めない。
出口・根拠・期間まで言語化できる情報源や相談先を持つこと。
④ 家計とセットで設計
投資は「余白」から。
保険・サブスク・通信費などを見直し、投資余力をつくるのが先決です。
👉 こうして投資を“家計設計の一部”として組み込むと、無理なく続けられます。
リスクを“管理可能”にする設計例
- 分散:資産(株・債券・金など)、時間(積立)、地域
- 目的別バケツ:
- 短期(1〜3年):現金多め
- 中期(3〜7年):債券/バランス型中心
- 長期(7年以上):株式比率↑・積立中心
- 出口のルール:目標リターンや取り崩し率をあらかじめ決めておく
👉 設計図があると「ブレても安心できる投資」になります。
よくある質問(FAQ)

Q1. 元本割れが怖い。
A. 短期で見れば誰でも怖いです。だからこそ積立×長期×分散。
必要な時期に必要な額を取り崩せる設計にしておけば怖さは管理可能です。
Q2. どの商品が正解?
A. 人それぞれ。目的・期限・許容リスクで変わります。
「みんなが良いと言っている」ではなく、**“自分の計画に合うか”**で選びましょう。
Q3. いくらから始めればいい?
A. ゼロより1,000円、1,000円より5,000円。小さく始めるほど継続しやすいです。
まずは固定費を1つ見直すことが近道になります。
まとめ:怖いからやらない → 知って備えるへ
- リスク=ブレ幅(不確実性)。ゼロにはできない
- 良いリスク(理解・分散・積立・長期)は取る価値がある
- 初心者は「小さく始める/時間を武器に/情報の質/家計とセット」
- 目的・期限・出口を決めると不安は“管理可能”に変わる
未来の自分と家族のために、今日の小さな一歩を踏み出しましょう。
お知らせ:学べる環境を用意しています
- 資産形成の無料勉強会:基礎から実践まで、初心者OK
- 個別相談:目標・期限・家計状況に合わせた設計を一緒に言語化
※スクール会員さまは引き続き無料枠あり。一般向けは一部有料化予定のため、興味のある方はお早めにどうぞ。